社員インタビュー | 採用は事業を“勝たせる仕事”
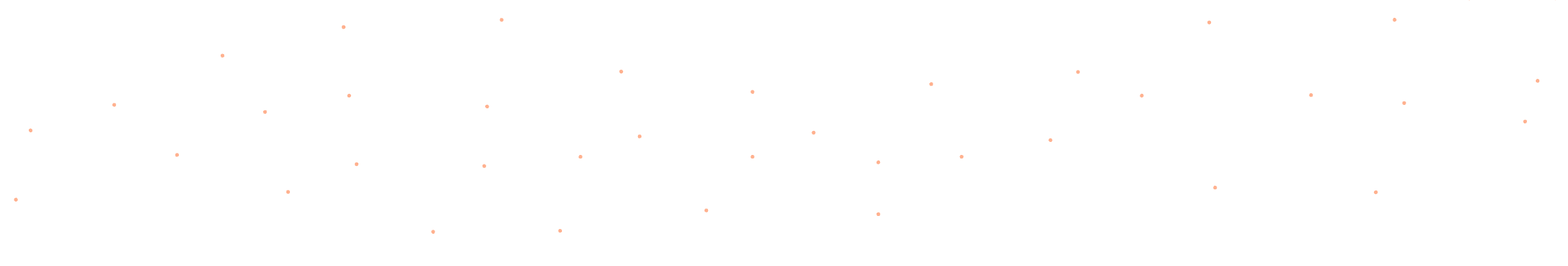

採用は“埋める仕事”じゃない。事業を“勝たせる仕事”だ ― Client Solutions Lead 植野 友介
採用や人事の現場で、「なぜこのポジションを採るのか?任せたいミッションを達成するためにはどんな経験とスキルが有効的なのか?」が語られずに画一的な求人票だけが走っていく。候補者要件は書けるのに、事業の成功にどう貢献する人材なのかを説明できない。エージェントから送られてくる母集団はあるのに、肝心なリーダー職・専門職だけはなぜか決まらない。
ZooKeepのClient Solutions Leadの植野裕介は、そんな“日本企業の採用の詰まり”を、10年以上さまざまな規模・業種の採用支援に携わる中で何度も見てきました。
彼がZooKeepにジョインした理由はシンプルです。「このまま “転職市場に出ている少ない人の取り合い” を続けていても、日本の採用は変わらない」。構造的な課題解決が必要だと確信したからです。ここでは、彼の原点・キャリアのターニングポイント・採用観・そしてZooKeepで実現したいことを、インタビュー形式でお届けします。
「採用を経営のど真ん中に置きたい」と考える方にこそ読んでほしい内容です。
1. “成果で語れ”の家で育った長男
1987年、山梨県生まれ。3兄弟の長男。
祖父は建設会社を兄弟で創業、両親は夫婦で調剤薬局を立ち上げ、という「自分で事業を起こすのが当たり前」という家で育ちました。
「幼い頃から“人に使われてるうちはダメだ”、“結果を出してから言え”、と言われてました。欲しいものも、ただでは買ってもらえない。スポーツで結果を出したら、テストで点を取ったら、初めて報酬がある。成果に対して報いる、というのが家のルールでした」
勉強もスポーツも“両方きちっと”が家の方針。中学受験には失敗し、親子で泣いた経験もありますが、それがかえって「勝負にこだわる」気質を強くしました。高校時代は陸上・駅伝で全国レベル、関東大会ベスト8、全国高校駅伝にも出場。その後、立命館大の理工学部で都市計画系を専攻します。
もともとは薬剤師の道も視野にありましたが、実家の仕事を見て「自分はやりたいと思わない」と感じたこと、そしてファッションやデザインなど“つくる側”への興味があったことから、理工系で“現実的な進路”に舵を切りました。
コンサルに落ちてRECRUITに拾われる
就職活動で志望していたのは、大手デベロッパーか、外資系の戦略・経営コンサル。「3年以内に成果が出なければ切られる」ような環境で急成長したいと考えていましたが、当時の外コン・外銀の門は狭く、ことごとく不合格。
「今でこそ採用が拡大してますけど、当時は戦略系コンサルファームや外資金融はほんとに厳選採用。正直、能力足りずで落ちました。だったら1年就活やり直そうと思ったら、親に“もう絶対ダメ”と言われて(笑)」
そんな時に出会ったのが、理系学生向けの新卒紹介サービス経由で案内された株式会社リクルートの契約社員ポジション。3年の有期雇用。親からは「契約社員でいいの?」と心配されましたが、本人はまったく気にしなかったと言います。
「パフォーマンスを出せば “残ってくれ” ってなるはずだ、って思ってた。僕は “勝つまでやる” タイプなので、そこで拾われなかったらそれまで。そういう感覚でした」
ところが、入社1年目は “鼻につく新人” だったと自分で振り返ります。戦略コンサルティングのトップファームで最終面接まで進んでいたがゆえに、「お前らとは違う」という態度がどこかに出ていた。指示通りにやって結果を出す同期を見ても「上に言われた事をやっただけでしょ、それは自分の実力じゃない」と自分は結果が出ていないにも関わらず斜に構えていた。
そんなとき、上司と同期に飲みの席で言われたひと言が効きました。
「 “お前、置いてかれてるぞ” って言われたんです。あ、このままだと評価されないし、チームに貢献できない、と思って姿勢を変えました」
さらに年度末、どうしても落としたくなかった案件を1本だけ落とし惜しくも目標未達、上司の前で悔し泣き。そこでスイッチが入り、2年目には統括部のMVPを獲得。以降はほぼ数字を外さなくなります。
「何をしたかというと、徹底的に数字を分解して、行動をデータ化したんです。“当たり前の行動が外れてないか” をまず確認して、その上でプラスアルファを乗せる。完全にデータドリブンで動いたら、伸びました」
3. “外を見ろ”
リクルート時代の若い自分に今メッセージを送るなら?そう聞くと、次のような回答でした。
「“お前、できてると思ってるけど大してできてないぞ”って言いますね。あと、“もっと外を見ろ”と。社内だけで競っても、それはあくまで社内の序列。外には外のトップがいる。視野を広く持て、って言うと思います」
これは、後に彼が日系企業の採用現場を見続ける中で感じた“日本の人事がなぜ強くならないのか”という問いにもつながっていきます。
4. 日本の採用、このままだと限界がくる
リクルートで大手から急成長のスタートアップのクライアント企業、スタッフレベルから役員クラスまでの役職など幅広く採用を支援していく中で、ある時点から違和感が強くなってきました。
「人材紹介のマーケットって、既に転職市場に出て動いてる人材をみんなで囲い込んで紹介してるだけなんですよ。表面的なKPIを追う、でも動いてる候補者はみんな同じ。これって世の中を変える人材のシフトにはなってないな、と」
「副業でお客さんの中に入ってみると、採用のリテラシーが全然ない。組織をどう作るかにも関心が薄いのに、“時価総額1兆円に行く”“グローバルでトップを取る”って言ってたりする。“いや、その状態じゃ無理でしょ”と正直思いました」
日本企業の多くは、採用や人事を「バックオフィスのひとつ」として扱い、経営側と連携する力をそこに配置していません。だから、採るべき人が誰かが本質的なレベルで言語化されていない。
そこで植野は「そういうクライアント企業を、レベルの高い採用ができる状態にまで引き上げるサービスを自分でつくった方が早い」と考えるようになります。
そんなときに出会ったのが、ZooKeepの共同創業者ケイシー・エーブルでした。
日本発で、世界に通用するHRテック・採用変革のモデルを本気でつくろうとしていたこと。「人事採用コンサルティング x 内製化に向けた実行支援 x HRテクノロジーという三位一体型のアプローチでないと日本企業は強くならない」という問題意識が共有できたこと。
これが、社員1号としてZooKeepに参画した決め手になりました。

5. 採用がうまくいかない本当の理由
インタビューの中で、彼は何度も「日本企業の採用が詰まる理由」をこう整理していました。
「誰を採りたいか」の解像度が低い
ベンチャーでも「CPOが欲しい」と言いながら、投資家に会ったら「いや今は採用すべきはここじゃないよね」と一発で覆る。つまり経営と採用の接続ができていない。採用を“人事の業務”に閉じ込めている
経営戦略や事業責任者側・人事採用チーム・社外の人材マーケットをつなぐ人が社内にいない。多くの企業で人事は「営業で成果が出なかった人の行き先」と見られていて、そこにエースを置いていない。表面的なKPIに満足してしまう
「エージェント経由で採用計画はほぼ達成できています」と言うが、事業インパクトの大きいリーダー・専門職に絞ると一気に達成率が下がる。にもかかわらず役職や求人の難易度を問わずにどんぶり勘定のKPI測定で「採用できている」と誤認識している。採用を外に丸投げしている
ターゲットしたい候補者データベースを自社で持たず、紹介エージェントのブラックボックスに依存しているので、人材市場の感覚がいつまでたってもインストールされない。営業で言えば直販は一切行わずに「ターゲットリストを毎回代理店に聞いている」状態。
6. ZooKeepでやっていること:TAチェンジマネジメント
こうした構造的な詰まりを解消するために、植野がZooKeepでリードしているのが「Talent Acquisition(TA)チェンジマネジメント」です。従来のRPOや人材紹介とは、スタート地点がまるで違います。
「僕らがやっているのは “その会社がダイレクトリクルーティングできるようになるまで引き上げる” ことです。まず事業計画から、どういうプロフィールの人がいないといけないのかを言語化する。並行して、本当に狙うべき候補者のリストを自社で持てるようにする。ここまでができて初めてEVP(Employee Value Proposition = 候補者目線で、企業と求人ポジションが従業員に提供できる総合価値の言語化)の設計や口説き方の話になる。前段ができてないのに“ブランディングを”と言ってもそりゃ候補者は来ないですよね」
彼が「ダイレクトリクルーティング」と定義するのは、こういう状態です:
「3人(候補者を)連れてきて1人決まる。これくらいのコンバージョン率が出て初めて “ダイレクトできてる” と言えると思ってます。自分たち(企業側)が欲しい人をわかってるから、最初からピンポイントで当てにいけるんです。欲しい人がわかっていないのに“ダイレクトやってます”って、言えないですよね」
だからZooKeepの現場では、人事採用側と事業部側の現場メンバー間のミーティングを設定し同席して、必要なステークホルダーを揃えて、意思決定の順番を整えます。
然るべきメンバーを集めて一緒に日々の“壁打ち”で「なぜこのような人材が必要なのか」を解像度高く理解する、そこに時間をかけます。
「事業部側の現場の人って頭がいいので、ちゃんとロジカルに “この採用戦略だと成功に至らないですよね” と伝えると理解してくれます。むしろCHROやCxOが頷いているのに、人事が耳が痛そうにしている、という場面のほうが多いですね」
理想的なプロフィール条件を満たす人材の紹介を採用チームに求めても、実際のマーケットでそのような人材の母数が少なすぎる、または自社の提示できる年収レンジでは厳しいとファクトベースで説明した上で、映画化された「マネーボール」のように複数の募集要項に分解してみて組織作りの成功確率を上げていく。
7. ツール導入を“形骸化させない”
ATS(採用管理システム)やAIソーシングを導入しても、運用が回らず、結局スプレッドシートに戻る。
HRテックに限らずSaaSの現場でよくあるこの失敗も、植野は「システムにプロセスを乗せ切れていないから」と言い切ります。
「入れた後の伴走のほうが大事なんですよ。入れて劇的に変わる、なんてたいてい起きない。導入の意味をステークホルダーと握る、定着させる、(採用力が)レベル2の会社がレベル5になりたいなら時間がかかる。この期待値をきっちり合わせるところまでやらないと、道具だけが浮いてしまいます」
また、植野は案件クロージングのために、下手にお客様に迎合しない。
理解が早いお客様には最初から本質論をぶつけ、そうでない場合はあえてRPO(採用代行サービス)のように敷居の低い形で入って、やって見せてあげて採用成果を出した上で「ほら言った通りですよね」という状況を作ってから改めて本質論をぶつける。それもすべて「社内に採用のノウハウが蓄積され、事業部側と人事の信頼関係ができる」ための設計です。
8. 「相手を勝たせる」
キャリアを通じて大切にしている価値観を聞くと、彼は2つ挙げました。
継続は力なり
インセンティブをつけて短期的なウルトラC施策を一時的に走らせて数字を作るより、仕組みをつくって積み上げるほうが強い。採用でも同じで、短期で“バーン”と成果が出ることはほとんどない。相手を勝たせる
「目の前の採用担当者が評価されて昇進したら、もっと大きい仕事について相談されるようになる。相手を出世させられるかどうかがポイントだと思ってます」
採用という仕事は、候補者本人だけでなく、その家族の生活も背負うことになる。
だからこそ、事業部に対しても「この求人は本当にその覚悟で出していますか?」と聞くべきだし、採用した人を“ワークさせる”ところまでコミットすべきだ、というのが彼の立場です。
9. これからの日本の採用
5〜10年先の日本の採用・人事については、こう見ています。
「体脂肪率の高い採用から、筋肉質な採用に変わるはずです。無駄に採ることができなくなる。限られた人でパフォーマンスを出し、ビジネスを伸ばす。だからこそ “誰を採るか” の解像度が今よりずっと重要になる。人事の中にあった採用機能は、経営・事業側に組み込まれていくと思います」
人口減少などの外部環境の変化が、人事採用を「バックオフィス」から「事業の維持成長に超クリティカルな戦略的機能」へと押し上げる流れになるという話です。
10. メッセージ
最後に「もし、経営とHRに関わるすべての人が目にする巨大な看板に、ひと言だけ書けるとしたら?」と質問すると、少し考えてから、彼はこう言いました:
「あなたは何がしたいんですか?」
採用でも、事業でも、キャリアでも、目的の自覚がないとズレていく。
「要員計画を枠埋めること」が「したいこと」ではない筈だが、それが目的になってしまっているケースが多い。
サッカーに例えると「左サイドを駆け上がってセンタリングでアシストできる人を採る」が目的であれば、人事採用としてやるべきことはまったく変わる。
その原点に立ち返る問いとして、この一文を選んだのでした。
編集後記:
ZooKeepが企業向けに提供しているのは、単なるATSでも、人材紹介でも、RPOでもありません。 「事業が勝つための人を、自分たちで見極めて口説ける状態」まで引き上げるための、テクノロジー+プロセス+伴走です。
◾️紹介社員のプロフィール(LinkedInプロフィールはこちら)
植野 友介(うえの・ゆうすけ)ZooKeep株式会社 Client Solutions Lead。リクルートキャリアにて、IT・コンサル業界、WEB業界の企業・候補者支援に従事。企業の採用支援を担当し、年間1000名以上の大規模採用プロジェクトにも貢献後、企業と候補者の両方を支援するコンサルタントとしても活躍。2022年にZooKeepに社員第一号として入社。日系大手企業や急成長スタートアップの組織開発・人材獲得を支援。
◾️おまけ:植野さんのお勧めの書籍やコンテンツは?
植野:「書籍はシンプルに【ハーバードビジネスレビュー】が良いと思っています。事業や組織について海外の実例や研究をベースに記載されており、採用実務という観点から引き揚げて経営視点を持ちながら実務に取り組めるようになるのではないかと思います。」
『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』は、世界的な経営学誌『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)の日本版で、1976年に創刊されました。経営戦略やリーダーシップ、イノベーションなど、ビジネス実務に役立つ論文や記事を提供し、企業のリーダーやプロフェッショナルに広く愛読されています:
植野:「動画系は pivotですね。小野さんや黒田さんが出ている回とか良いと思っています!」
小野壮彦(グロービス・キャピタル・パートナーズ ディレクター)登壇エピソード例:【世界標準の採用】
黒田真行(転職コンサルタント、ルーセントドアーズ代表)登壇エピソード例:【採用ビジネス、2030年までの未来予測】

