社員インタビュー | 青木岳彦さん、ZooKeepへ
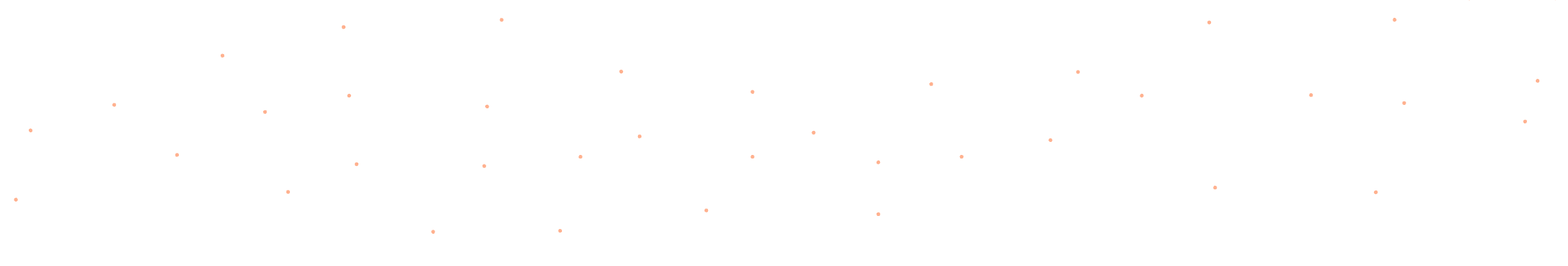

経験豊かな人事プロフェッショナルが語る「組織に向き合い続ける理由」と「これからの挑戦」。
国内外のグローバル企業やPEファンド傘下の企業で、組織再編や人事改革を担ってきた青木岳彦さん。日本マクドナルド、SEIYU、Marelli、ブリヂストン(本社&アメリカ駐在)など数々の企業の変革期に人事責任者として携わり、実行の最前線に立ってきました。
そんな青木さんが、2024年ZooKeepにジョイン。これまでのキャリアとは一見異なるスタートアップという環境を、どのように捉え、どのような思いで参画されたのか。その背景と展望について伺いました。
変革の現場にこそ学びがある。スタートアップという選択
——まずは、なぜZooKeepというスタートアップへの参画を決められたのかを教えてください。
スタートアップに関わるのは初めてではないのですが、今回のZooKeepとのご縁には、特に惹かれるものがありました。代表のCaseyが語るビジョンに、共感するところが多かったんです。「日本発の組織が、世界で戦えるようになるにはどうすればいいか?」その問いに真剣に向き合おうとしている姿勢に、心を動かされました。
そして、組織の中で働く人にとっても、その成長の場となるような環境をつくっていきたいという思いが、自分のこれまでの仕事観と重なりました。企業の規模やフェーズに関わらず、現場にいる人たちの声を聞き、一緒に考え、前に進んでいく。そんな働き方を、ZooKeepでもしていけたらと思っています。
すべてを自分たちで決めていくからこそ、創造性が問われる
——これまでのご経験の中で、特に印象に残っているプロジェクトはありますか?
たくさんありますが、ブリヂストン時代に米国で新工場を立ち上げたプロジェクトは、いま振り返っても大きな学びがありました。当時は、日本式のやり方がそのまま通用する時代ではなく、アメリカの企業文化や生産性のスタイルに真剣に向き合いながら、新しいやり方を模索する必要がありました。
既存の枠組みにとらわれず、他社のベストプラクティスを参考にしながら、自分たちなりの手法をつくりあげていく——そのプロセスに、創造性とチームの力を感じました。そうした経験は、今でも大切にしています。
テクノロジーは、人の力を引き出す道具であるべき
——ZooKeepの「テクノロジー × ヒューマン」のモデルについて、どうお考えですか?
ZooKeepのユニークさは、単にツールとしてのATS(採用管理システム)を提供するのではなく、その使い方を通じて、採用や組織全体のあり方に向き合っているところにあると思います。
私自身、エンジニアのようにシステムを作ることはできませんが、人や組織が抱える課題に向き合い続けてきた経験は、少しはお役に立てるのではと思っています。採用プロセスを「効率化」することが目的ではなく、採用という営みの中で、組織の本質的な力をどう引き出していけるか——そんな視点でZooKeepのプロダクトやサービスと向き合っていけたらと考えています。
“人事を変える”ではなく、“人事が組織を変える”という発想を
——これからの日本企業にとって、人事はどのような役割を果たすべきでしょうか?
私は、組織づくりの真ん中に人事があるべきだと考えています。とくにPEファンドとの仕事を通じて実感したのは、企業価値を本気で上げていくためには、成長のストーリーが不可欠であり、その軸に「人と組織」があるということです。
でも残念ながら、日本ではまだそこに十分な投資や議論がなされていない場面も多い。そこに対して、ZooKeepのような存在が、テクノロジーと現場支援の両面から伴走していくことには、大きな可能性があると感じています。

“人事の仕事がもっと面白くなる” そう思える瞬間をつくりたい
——最後に、ZooKeepの仲間や、これから出会うパートナーに向けてメッセージをお願いします。
ZooKeepと一緒に取り組むことで、人事や採用の仕事がより意味のあるものに感じられたり、前よりも少しだけ「面白い」と思えるような、そんな体験をつくっていけたら嬉しいです。
私自身、これまでのキャリアの中でいろんな方に出会い、たくさんの対話から学ばせてもらいました。その経験を活かして、ZooKeepのチームやお客様と一緒に、より良い組織づくりに向けて前に進んでいければと思っています。
最後にひと言、掲げたい言葉があるとすれば
“Have Fun. People Success = Business Success. Everybody has the potential to perform.”
それが、私の仕事のスタンスそのものです。
LinkedInプロフィールはこちら

