社員インタビュー | ジョーダン・ジャジョーラ、GoogleからZooKeep へ
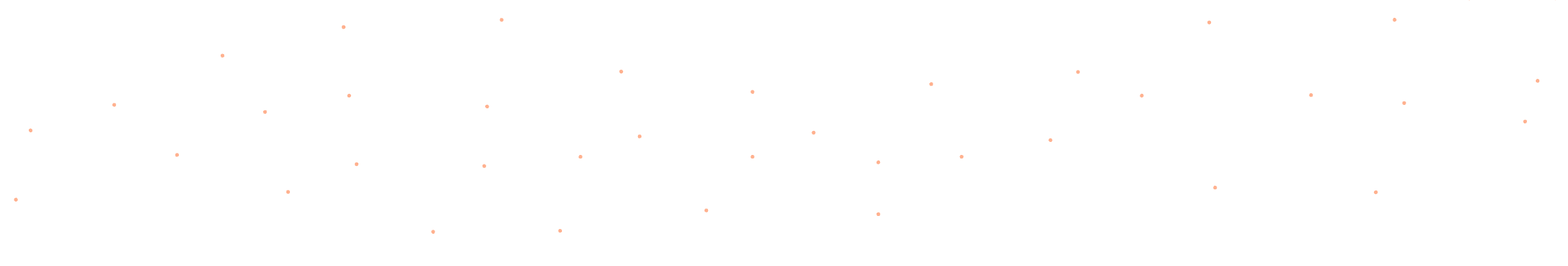

オハイオから東京へ、人と仕組みの交差点で育まれた探究心
——まずは、出身地や生い立ちについて教えてください。
米国オハイオ州ケント。静かな大学町で育ったジョーダン・ジャジョーラは、幼い頃から「人」と「仕組み」の両方に強い興味を持っていました。
父は医療研究の統計学者、母は幼児教育の専門家。さらに家族のルーツであるレバノン系の文化は、温かい人間関係や語り合いの場を大切にするものでした。ジョーダンの価値観は、まさに「人 × プロセス × 目的意識」の重なりから形成されたといえます。
若い頃はシェフを夢見て厨房に立っていましたが、次第に「改善」という考え方に惹かれていきます。大学時代、アルバイト先のイタリアンレストランでカイゼンの考え方を応用し、食材管理フローを再設計。食材コストを約30%削減したこの経験は、のちのキャリアの原点となりました。
採用という“人とシステムが交わる領域”との出会い
——どのような経緯で採用に関わることになったのですか?
日本文化に興味を持ったことから来日した後、ジョーダンのキャリアは英会話ビジネスのオペレーション部門から始まります。当時まだ一般的ではなかった「HRのデジタル化」を先駆けて自ら実践し、英会話教師のシフト管理や勤務スケジュールをデジタル化。その後、また米国に戻りふとした偶然からシリコンバレーで人材紹介業に携わり、ソフトウェアエンジニアからゲームデザイナーなどの採用を支援しました。
なかでも彼の転機となったのは、ゲーム業界では名の知れたスクウェア・エニックス社での経験です。
「目の前で、内定したエンジニアが開発チームの “文化” と ”プロダクト(ゲーム)” を強く影響していく瞬間を見たんです。採用とは単に人材を獲得する行為ではなく、組織の未来を形づくる行為だと気づきました。」
Googleで学んだ「スケールする採用」の本質
スクウェア・エニックス社での実績が評価され入社したGoogle Japanでの7年間、ジョーダンは日本と韓国におけるエンジニア採用を統括。モバイルアプリ黎明期における、母数が非常に限られていた日英バイリンガルな iOSエンジニアの採用という、極めて難易度の高いミッションに挑みました。
彼がそこで得た教訓は明快です。
「採用の成功を支えるのは “明確さ・整合性・シンプルさ” の3つ。どんなに優秀なリクルーターでも、共通の枠組みがなければデータから学べない。」
一方で、多くの組織が「ビジネス目標と採用設計の乖離」に悩む現実も見てきました。
「採用は実は営業に似ています。ただし、営業には最終的にはCFOや経営企画によって定められる“成果へのコミットメント”がある。採用でも “活動量” ではなく “成果へのインパクト” で語るべきです。」
さらに世界が同時多発的に悩まされたコロナ期には、Google社内のグローバルCOVID-19タスクフォースに参加し、世界中のGoogle社員のビザ対応や採用継続を支援するフレームワーク作りと運用管理に従事。混乱の中で “粘り強く仕組みを回す” 経験を積みました。

ZooKeepで描く「次世代ATS=変革エンジン」の姿
——ZooKeepに参画した背景について教えてください。
Zookeepに参加した理由は3つの大きな要素がありました。
まず1つ目は、複数の企業の採用課題を解決できる機会。
Googleでは毎年採用する人数が大きく変動するにもかかわらず、自分の採用チームのサイズを柔軟に調整することができませんでした。日本の労働法の制約もあり、人手が足りない時期も余剰な時期も、同じ体制で対応せざるを得なかったんです。そこで「優秀なリクルーターを8〜10ヶ月だけ柔軟に受け入れられたら」と考えるようになりました。Zookeepでは、コンサルティング的なアプローチで企業の課題を理解し、単なる人材リソースの提供ではなく、本質的な問題解決ができる。これが非常に魅力的でした。
2つ目は、採用テクノロジーの改善。
当時、GoogleでさえもATSは使いづらいものでした。社内システムは複雑すぎて、経験豊富なリクルーターでも、まるで操縦したことのない飛行機のコックピットに座らされたような感覚でした。候補者を正しく検索することもできず、データを整理するためにExcelでスクリプトを書かなければならないこともありました。市場にある他のツールも試しましたが、どれも満足のいくものではありませんでした。Zookeepでは、日常的に採用業務を行う人が直感的に使える、シンプルで効率的なツールを作れる可能性がありました。
そして3つ目は、日本の採用市場特有の課題への取り組み。
日本では新卒採用や終身雇用の文化が根強く残っており、海外市場と比べると未だに中途採用の環境が十分に整っていない点。GoogleでiOSエンジニアの採用に苦労した経験から、この問題はCovid後にさらに深刻化すると予感していました。クラウド技術やSaaSプラットフォームへの需要が高まる中、日本にはその基盤がありませんでした。長年日本で暮らしてきたジョーダンにとって、日本の採用市場を支援することは個人的にも情熱を感じる分野でした。
これら3つの要素―問題解決の機会、テクノロジー、そして日本市場への貢献―が重なり合い、Zookeepで働くことに大きな魅力を感じたのです。
彼が目指すのは、単なるATSではなく、“Talent Acquisition Platform(人材獲得プラットフォーム)”の実現。グローバルHRテクノロジーを取り込みつつ、日本企業の現場に深く適応させる、その挑戦の先頭に立っています。
技術選定の基準も明快です。
リクルーターの成果に対する科学的な効果
他ツールとの高い連携性
日本の採用文化に適応したUI/UXのわかりやすさと透明性
トヨタのプロジェクトから学んだ「自走する採用組織」
前職である、ZooKeepのグループ会社でもあるMeshdでは、トヨタ関連企業「Woven by Toyota」での採用プロジェクトをリードし、クライアント企業の人材紹介エージェント依存からの脱却を支援。採用チームが自走できる仕組みづくりを進めました。
「重要なのは明確さとオーナーシップです。役割・指標・コミュニケーション構造を整理すると、チームは驚くほど速く動けるようになる。」
採用の未来、標準化と共通言語化へ
——どんどんテクノロジーが浸透していくHR領域ですが、採用の未来についてどのように考えていますか?
採用が今後どう変わっていくか、という質問に対してジョーダンは冷静です。
「AIが置き換えるのはリクルーターではなく、悪い採用習慣です。自動化で雑務を減らし、リクルーターは関係構築・ストーリーテリング・課題解決に集中すべき。」
彼が真の変革として重視するのは、生成AIではなく「オペレーションの標準化と採用関係者のデータリテラシー」。
営業部門がSalesforce提唱の「The Model」によって共通言語を得たように、採用領域も共通したオペレーション言語を持つべきだと語ります。
「効率が成功を導く」
——仕事やビジネスにおいて大切にしている概念や原理原則はありますか?
ジョーダンの信念は、一言に凝縮されています。
“Efficiency equals success”(効率は成功を導く)
ここでいう効率とは「速さ」ではなく、「整合性」「明確さ」「伝達の精度」。トヨタ式カイゼンの哲学と、Googleで培ったプロセス思考の融合です。
「採用は、正しく設計すればどこまでも改善できる領域。ブリーフィングからフィードバックまでの全てが、オペレーショナル・エクセレンスへの一歩です。」
もし日本やASEANの採用リーダーに一言伝えるなら?
「まず “明確さ” に集中してください。優れた人が優れた成果を出せる仕組み、環境を用意してあげること、それこそが採用リーダーの仕事です。」
最後に:“採用はアートであり、サイエンスである”
厨房の最適化からグローバル採用システムの構築まで。
ジョーダンのキャリアは「職人の緻密さ × 科学者の論理 × リーダーの共感力」の融合そのものです。
ZooKeepが掲げる People・Process・Platform の思想は、まさに彼の歩みに重なります。
そしてその理念は、次世代のHRテクノロジーを形づくる原動力となり、採用という領域に“進化し続ける効率”をもたらしています。
Jordan Jarjoura(ジョーダン・ジャジョーラ) の LinkedInプロフィールはこちら
米国オハイオ州出身。Square EnixやGoogle Japanにて長年に渡り、米国・日本・韓国におけるエンジニア採用を統括。Googleではモバイルアプリ黎明期における日英バイリンガルiOSエンジニアの採用という高難度ミッションをリード。同社では約10名からなるグローバルCOVID-19タスクフォースにも参加し、世界中のGoogle社員のビザ対応や採用継続を企画および運用管理。その後、Meshdにてトヨタグループ企業「Woven by Toyota」の採用コンサルティング & RPOプロジェクトを担当し、採用組織の自走化を実現。現在はZooKeepにて自社ATS製品のプロダクト責任者として、次世代 Talent Acquisition プラットフォームの構築を牽引している。

